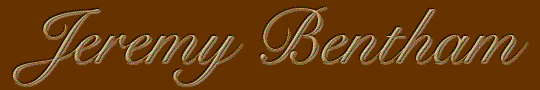はじめに―ベンサム・コレクション
本学所蔵のベンサム・コレクションは、ロンドン大学の有力校ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンおよび大英図書館を合わせたロンドン以外では、世界で最も充実したコレクションということができる。その理由は、同コレクションには、ジェレミ・ベンサムが生前に出版した著作やパンフレットのほとんどすべてが所蔵されているだけでなく、それらのなかには今日、世界の各図書館に分散して数冊しか確認されていない著作やパンフレットが集中して少なからず含まれていることにある。さらに、同コレクションには、上記ユニヴァーシティ・カレッジに設置されているベンサム・プロジェクトにより、長年にわたって収集されてきた書簡類にも欠落しているベンサムに関わる書簡等が含まれていることも、同コレクションが注目される大きな理由のひとつとなっている。
『流通年金論』パンフレットのゆくえ
そのなかでも、特に注目すべきもののひとつが、ここに紹介する『流通年金論Circulating
Annuities』と題された小さなパンフレットである。このパンフレットはいわくつきのものであり、今日、諸外国の主要図書館を含め本学図書館に所蔵される1冊のみが確認されているにすぎない。『流通年金論』という奇妙な表題である点を別にしても、それはもともと「数部」のみが印刷され、少数の人びとに配布されたものであった。本学に所蔵されているパンフレットは、明らかにその1冊であり、本文48頁(第4章の途中まで)に2枚の表が挟み込まれた仮綴である。したがって、それには表紙もなく、キャプションタイトル(見出し表題)のみが付され、著者、出版地、出版年、印刷屋等も印刷されないまま、ごく限られた範囲の人びとだけに私的に配布されたと考えられる。
このパンフレットは、かつて大英図書館にも所蔵されていたが、第二次大戦時の空襲により消失してしまい、それ以後、その所在はどこにも確認されていなかったものである。
現在刊行されつつある新『ベンサム全集』まで、過去1世紀以上にわたって唯一のベンサム全集であり続けたバウリング版『ベンサム著作集』(11巻、1838-43年)第3巻にも一部、本パンフレットが利用されているのを確認しうる(106-120頁)。その箇所の目次下欄外には、次のような編者注が記されている。「以下の著作が編集された草稿は、ベンサムによって1800年に書かれ、―その時、最初の4章の主要部分が印刷された。編者は、それらの4章については、ただ1冊のみを発見することができたにすぎない。」
ここで指摘されている「1冊」とは、明らかに大英図書館所蔵の1冊であり、それはベンサムが当時の有力な急進主義者フランシス・プレイスに送ったものであった。
その後、1世紀以上たって、ケインズの依頼と財政支援の斡旋を受けて『ベンサム経済学著作集』(3巻、1952-54年)の編集と刊行に取りくんだスタークによれば、同パンフレットは上記のテーマに関するベンサムの見解の「最終版」を示すものとして、同『著作集』に収録するのが望ましいと考えられた。しかし、それは「もっとも熱心な探索」にもかかわらず、1冊も発見することができなかった。つまり、そのパンフレットは、バウリングがベンサムの遺言にしたがって『ベンサム著作集』を編纂する段階(1830年代)では存在していたが、スタークが1940年代に新たに『ベンサム経済学著作集』を編集する段階では、すでにどこにも見いだすことができなかったということである。それから半世紀以上たった今日も、その発見は報告されていない。
その意味でも、本学で所蔵されているパンフレットはきわめて貴重であり、現在ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンから中央大学に対して提案されている新『ベンサム経済学著作集』(4巻、オクスフォード大学出版予定)の共同編集と出版―それは、スターク版の欠陥を是正し、ベンサム経済学の決定版を提供することを意図されている―にとっても重要な資料のひとつになるだろう。
ベンサムの著作の特異性
一般に、ベンサムの著作やパンフレットは複雑な経過をたどって出版された。ベンサムは生涯を通じて「書かざる日はなし」といわれるくらい、執筆に専念し、膨大な草稿を書き残した。しかし、彼の著作やパンフレットの多くは、彼の回りに集まった「弟子」といわれる人びとによって、それらの草稿から編集され、出版された。彼自身の手によって出版された場合でも、しばしばそれが執筆された時期、印刷された時期、出版された時期が大きく異なるという特徴をもっている。彼の有名な『道徳および立法の原理序説』にしても、1770年代に書かれ、1780年に印刷されたが、出版されたのは1789年であった。しかも、ある場合には、出版の時点で、表紙を付けかえたり、本文より長文の「序論」を付したりしている。そのため、彼の著作やパンフレットは、多くの場合、書誌学的に見ても複雑な構成を示している。本学に所蔵される著作やパンフレットは、これらの点を解明するうえでも貴重な価値をもっている。
しかし、ベンサムの草稿の多くは、今日なお未刊のままに残されており、刊行されている場合でも、しばしば膨大な草稿の一部分のみである。その典型が、『流通年金論』と題される本パンフレットであるといってよいだろう。そのパンフレットは、前述のように本文48頁と2枚の付表からなるにすぎないが、ベンサムが同一表題のもとに執筆した草稿は、ほぼA版の大きさの紙葉で1400枚にのぼるといわれている。したがって、本パンフレットは、そうした分量の草稿からすればごく一部にすぎない。しかし、本パンフレットは、ベンサムが当時、ピット内閣のもとで大蔵大臣補をつとめたジョージ・ローズ、およびそれに続くアディントン内閣のもとで同じく大蔵大臣補をつとめていたニコラス・ヴァンシタト宛に、政府が採るべき政策として提案することを意図して執筆した草稿の重要な一部を含んでいた。彼は、そのため1799年後半から1800年の後半までの1年以上にわたって、彼にとっては異例ともいうべきほど、その執筆に専念した。その提案は政策としては採用されずに終わったが、その結果として残されたのが、上記のような大部の草稿であった。しかし、それらもまた、ベンサムの経済学および経済政策論草稿全体から見れば、一部をなすにすぎないものであった。
ベンサム法体系と経済思想
ベンサムが経済学および経済政策論の研究に取りくんだのは、主として1786年から1804年までの18年間であった。もちろん、それ以後においても、彼は経済問題への関心からまったく離れたわけではなく、晩年にいたるまで折にふれ政府支出の削減や効率化の問題などを取りあげ続けた。しかし、彼が経済問題を中心にすえて、それらの研究と執筆に大きなエネルギーを注いだのは、上記の18年間であり、それは彼にとっても38歳から56歳という人生の最も充実した時期に属し、今日伝えられている経済学関係草稿の大部分は、この時期に執筆されたものである。
前述のように、彼の有名な著作『道徳および立法の原理序説』は、1770年代に書かれ、1780年に印刷されたが、出版されたのはようやく1789年になってからであった。出版にさいして、ベンサムは新たに「序文」を付け加え、印刷してから10年近い歳月も放置した理由を述べている。ベンサムによれば、『序説』は「刑法」のための導入を意図して執筆されたが、同書は「刑法」の前提となるべき「民法」についてまったく論じていないという重大な欠陥をもっていた。このように述べつつ、ベンサムは改めて10部門からなる自己の法体系の構想を示している。そして、事実、その体系では「民法」が全体の冒頭(第1部)に置かれ、「刑法」が第2部に置かれるという構想が示されている。その点は別にしても、注目すべきは、それらの体系の第8と第9の部門に、それぞれ「財政」と「経済」という項目が置かれていることである。ここから理解されるように、「財政」や「経済」の問題は、ベンサムが法体系を構想しつつあった早い時期からすでに考察の対象として視野にいれられていたということである。
スミス『国富論』とベンサム
しかし、彼が最初に取りくんだ経済問題は、当時、法律によって最高利子率が制限され、それに賛成したアダム・スミスを批判することであった。彼は、その仕事を『高利擁護論』(1787年)として出版し、そのように利子率を制限することは、自由な競争を妨げ、むしろ経済と社会の発展にとってマイナスであることを論じた。しかし、そこでの議論は、ベンサム自身が認めているように、経済学的というよりは、むしろまだ法的な視点、すなわち、市場での自由な貨幣取引の結果として成立する高利がなぜ禁止されなければならないのか、そのような禁止は貨幣を貸付ける人々の権利(所有権)の侵害を意味するのではないか、という視点からなされていた。
この著作はかなり注目されたにもかかわらず、ベンサムが本格的な経済学研究へと向かっていったのは、1790年からであった。彼は、それまでアダム・スミスの『国富論』をくり返し読み、ちょうど敬虔なキリスト教徒が聖書を暗記するように、『国富論』を隅から隅まで暗記するほどであったといわれている。そうした知識にもとづきながら、彼は最初、ピット内閣の植民地政策を批判し、植民地放棄論を展開するなかから、本格的な経済分析へと進んでいった。彼の立場は、一面では『国富論』を継承し、他面ではそれを自由競争論の視点からいっそう徹底しようとするものであった。したがって、彼は政府による経済への介入を可能なかぎり少なくすることを主張し、政府のなすべきこととなすべきでないことを厳格に区別する作業に取りくんだ。そして、それらをやや体系的にまとめ、ひとつの著作として論じたのが、ベンサムの初期経済(政策)思想の集大成ともいうべき『政治経済学便覧』(1793-95年)であった。
累積する公債問題
しかし、ベンサムの関心は当時、大きな問題となりつつあった公債問題へと急速に惹きつけられていった。アメリカ独立戦争、対仏戦争とそれに続く対ナポレオン戦争のなかで、公債が累積し、政府財政をいかにまかなうかが大きな問題となっていた。そのため、彼は『政治経済学便覧』を十分完成させないまま、財政問題へと関心を移行させ、財源問題について政府に提案する政策を次々と執筆した。そして、「租税は悪である」という考え方を基本視点としながらも、間接税としては、生活必需品をのぞく消費財や奢侈品への課税、直接税については、税負担の公平原則のもとに、貨幣取引や債券取引を独占し、それまで課税されていなかった銀行業や金融仲介業にも課税することが適切であると主張した。また、彼が腐心したのは、税負担の増大をともなうことなしに、歳入を増加させる方法を考案することであった。
その方法として彼が提起したのは、封建法を復活させ、遺言が残されていない場合や、比較的近い親族の相続者がいない場合、その遺産は国に復帰するものとし、それを競売に付すことによって歳入の増加をまかなうという方法であった。
ベンサムはさらに、より積極的に、累積した政府債務(公債)を削減し解消する方法として、貨幣取引に関わる諸業務(紙幣を含む貨幣の発行券)や保険事業(年金の取扱い)を銀行や民間諸団体から政府の手に移管し、それらを通じて公債を償還し、政府を累積する債務から解放する方法を考案し、それを政策として提案する方向へと進んでいった。それらのうち、とくに後者の年金業務を政府の手に移管した場合の詳細について論じたものの一部が、本パンフレットである。
『流通年金論』の内容
「流通年金」とは、簡単にいえば年金証書を利子付きで紙幣として流通させることを指している。ベンサムは、1799年夏頃から1800年の後半にかけて、彼にしては異例ともいうほどの熱心さで執筆に専念し、1400枚という膨大な草稿を書いた。したがって、「流通年金」構想は、ベンサムの経済思想、とりわけ経済政策を考えるうえできわめて重要な位置と意義をもっている。
しかし、ベンサムは1800年半ば頃になって、執筆した草稿のままでは量的にも一般の人びとが読むには不適切であると判断し、9月から10月にかけて、それらの内容をより簡潔に要約し、再度『流通年金と題される冊子の要約ないし圧縮した見解』という草稿を執筆した。実は、本パンフレットはこの『見解』の最初の4章(第4章は途中まで)と2枚の表を印刷したものである。
『見解』は、バウリング版『著作集』第3巻にも収録されたが、表題が変更され、内容もベンサム自身の計算例などが削除されたりしている。
ベンサムは、「流通年金」の提案によって、従来の国庫証券より低い利子率で、イングランド銀行券にかえて年金証書を紙幣として流通させ、それによって国庫財源を確保し公債の償還を促進しうる仕組みを示した。そして、それが生命保険としての役割を果たすと同時に、利子付であることから、下層階級の貯蓄と生活の安定、さらには社会の安定にも資することを強調している。
ベンサム経済思想の転換点としての『流通年金論』
「流通年金」計画の目的のひとつに、下層階級に節約の精神を植えつけ、彼らの生活の安定を図ることが含まれていたように、ベンサムはつねに下層階級や貧民の救済という視点をもち続けた。事実、彼は1790年代半ばに救貧問題に取り組み、大部の救貧法論草稿を執筆している。ベンサムの経済思想の特徴を考えるうえで、貧民救済問題は重要な意味をもっている。スターク版では、この重要な側面が事実上無視され、ベンサムの経済思想がもっていた本来の構造や性格の把握を困難にしている。
ベンサムが「流通年金」論の構想を取り下げることになったのは、ヴァンシタト大蔵大臣補をはじめ、政府からそれを考慮するという明確な解答が得られなかったことにもよるが、より本質的には、ベンサム自身がそれを考えぬくうちに、そのような紙幣政策がインフレを生じさせ、下層階級と貧民に大きな犠牲を強いる危険があることに気づいたからであった。それを機会に、ベンサムの経済学および経済政策研究の主要な関心は、紙幣発行とインフレーションとの関係の究明へと向うことになった。
ベンサムが「流通年金」論の構想を取り下げることになったのは、ヴァンシタト大蔵大臣補をはじめ、政府からそれを考慮するという明確な解答が得られなかったことにもよるが、より本質的には、ベンサム自身がそれを考えぬくうちに、そのような紙幣政策がインフレを生じさせ、貧民に大きな犠牲を強いる危険があることに気づいたからであった。それを機会に、ベンサムの経済学および経済政策研究の主要な関心は、紙幣発行とインフレーションの関係の究明へと向うことになった。
その意味で、「流通年金」論の構想は、ベンサムの経済思想にとって転換点をなすものであった。今日、世界で1冊しか発見されていない本パンフレットは、転換点における彼の経済思想がどのような性格をもち、また政策としてどのような形で具体的に提示されたかを示しており、それを実証する資料としてもきわめて貴重である。
(中央大学経済学部教授 音無通宏)
|