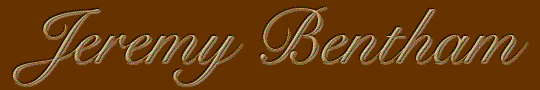
ベンサム・コレクションとブルーム書簡
誤解されたベンサムジェレミ・ベンサム(1748−1832)は近代法の体系的創設者として知られている。しかし、彼の関心は、法学を中心としながらも、議会改革論や司法制度などさまざまな分野の機構改革論、経済学、倫理学、教育論、論理学、言語論、宗教論等々といった広範な領域におよんでいる。その意味で、彼はたんなる狭い意味での法律学者ではなく、何よりもまず近代功利主義の立場にたつ哲学者であり思想家であった。ベンサムの思想や理論については、従来「功利の原理」のもとに人間を物欲的な損得づくで行為するものとみなす卑俗な人間観にたつものであり、「最大多数の最大幸福」の名のもとに少数者や弱者の権利を犠牲にするものとする誤解や批判がなされてきた。しかし、そのようなベンサムの理解は、現在進められている『新ベンサム全集』の刊行を通じて大きく変えられようとしている。 ベンサムは職業につかず、84年の生涯を通じて「書かざる日はなし」といわれるほど思索と著述に専念した。そのため、彼は膨大な草稿を書き残した。それらの草稿の大部分はロンドン大学ユニヴァーシティ・カレッジに保管され、それらだけでもA4版の紙葉で約6万枚におよぶ。(宗教関係の草稿は大英図書館に保管されている。)それらの膨大な草稿に比べれば、彼が生前に著作として出版したのはごく一部にすぎず、しかもその多くは彼の回りに集まった「弟子」たちの手によって編集され出版された。 ベンサムの死後、出版された著作と草稿の出版権は「完全な全集」を刊行するという条件で遺言執行人となったジョン・バウリングの手にゆだねられた。バウリングは、ベンサムの指示にしたがって、自ら指名した人びとの協力をえて、それらを編集し1838−1843年エディンバラのテイト社から11巻本として刊行した。そして、このいわゆるバウリング版『ベンサム著作集』が、以後1世紀以上にわたってベンサムの思想を表わすものと受けとられてきた。しかし、同『著作集』は、形式的にも内容の点でも多くの欠陥をもっていた。 形式の点では、各頁が左右二欄に区分され、しかも本文は今日の基準でいっても9ポイントに満たない小さな活字で印刷され、脚注はさらに小さな活字で印刷されていた。そのため、それは多くの人にベンサムの思想や理論を近づきがたいものにする結果をもたらした。いっそう重大なのは、その内容上の欠陥であった。11巻という分量ではやむをえないとはいえ、同『著作集』には、ベンサムの思想や理論を正しく理解するうえで重要な著作や草稿・パンフレットが少なからず含まれないままに残された。例えば、ベンサムが初期から一貫して抱き続けたイギリス国教会批判やキリスト教批判に関する著作や草稿がすべて除外されたのは、その典型的な例のひとつである。彼の同性愛擁護論についても同様であり、他にも多くの例が見られる。それだけでなく、同『著作集』に含まれた著作それ自体についても、それらが果たしてベンサムの草稿に忠実であるか否かが大きな問題とされている。このような旧『著作集』の重大な欠陥を是正するために進められているのが、『新ベンサム全集』の刊行である。 新しいベンサム像の出現『新ベンサム全集』は、総計70数巻予定され、現在までのところ「書簡集」を含め20数巻、全体の3分の1程度が刊行されたにとどまっている。その最大の理由は、ベンサムの草稿が解読するのにきわめて困難なことによる。しかし、そのような限られた『新全集』の刊行によってさえ、従来のベンサム解釈と功利主義理解が大きく変えられようとしている。ベンサムの哲学が人間を物質的な欲得づくで行為するものとする「豚の哲学」であるという解釈や少数者の権利や弱者を犠牲にしてもよいとする学説であるという先のような批判に対して、彼の功利主義学説の基本概念である「幸福」概念にしても、「安全」「生存」「豊富」「平等」というより具体的な内容に即して理解されるべき性格のものであり、ベンサムこそ女性の権利の平等性を主張するとともに、私有財産権の枠内で弱者や貧困な人びとの権利や利益を擁護する立場にたっていたことが明らかにされている。また、彼が「自己配慮的原理」とともに「他者配慮的原理」をも重視していたことや、人生行路において「期待」の実現にとって「落胆防止原理」が果たす役割を重視していたことなども指摘されている。こうして、彼は、少数者や弱者をも含めて、期待・失望・不安・恐怖等々といった感情や情念が人間にとって大きな役割を果たすこと、そして、とりわけ人間の自由が「落胆防止」や「期待」の実現に依存することを重視しつつ理論を構築していたことが明らかにされてきている。 ベンサム功利主義学説のより具体的な概念である「生存」「安全」「豊富」「平等」という4つのうち、彼がもっとも重視したのはいうまでもなく「生存」と「安全」である。「生存」なくして「安全」はありえないし、「安全」なくして「生存」はありえないからである。この点で、ベンサムにとって経済学および経済政策研究は重要な意味をもっていた。事実、彼は40歳代から50歳代という人生のもっとも充実した時期に、それらの研究と執筆に取り組んだ。それは、利子論から始まり、赤字財政の解消と国民負担増を伴わない財政調達論、新紙幣論、年金(証書)流通論、紙幣の過剰発行弊害論、食糧価格設定論、経済学原理、植民・貿易論など多岐にわたっている。その間、彼が重視し続けた問題は貧民救済問題であり、貧困問題は彼にとって社会の基本に関わる重要問題であった。こうした彼の問題関心と主張は、今日的課題の解決にも資する側面を多く持つとともに、後のケインズの主張とも共通する面をも持っていた。 このような彼の経済思想および経済政策論をも含めて『新ベンサム全集』の刊行が進行するにつれて、従来のベンサム像と功利主義理解の刷新がさらに決定的になることが予想される。その意味で、『新ベンサム全集』の一環として中央大学に対してユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンから提案されている『ベンサム経済学著作集』(4巻)の共同編集・共同出版は、大きな意義を持っている。 ベンサム・コレクション中央大学図書館に所蔵されるベンサム・コレクションは、1985年と1986年に購入されたものを母体としている。前者は主として英国の急進派下院議員であったフランシス・バデットの蔵書からなり、後者はアメリカの政治家でベンサムとも交流のあったエドワード・リヴィングストンの蔵書から構成されている。その後に購入されたものを合わせ、同コレクションにはベンサムの生前に印刷され出版された著作のほとんどすべてが含まれている。それらの中には、今日世界でその存在が3冊のみ確認されているにすぎない著作や中央大学で所蔵される1冊のみが今日世界で確認されている唯一のものである著作なども含まれている。 ベンサムの著作やパンフレットは、一般にきわめて複雑な経緯をたどって出版された。ベンサムは草稿を書いていくなかで、主題を細かく分類し、その分類したより細かな項目について書き進めていくうちに、本来の主題そのものから遠く離れてしまい、再び立ち返ることなく、錯綜した筋道の中でしばしば執筆そのものを中断し放棄してしまった。そして、そのようにして書かれた草稿が、当時の政治状況からくる必要に応じて「弟子」たちの手に渡された。ベンサムの名が広く知られるようになったのは、まず(イギリスにおいてではなく)ヨーロッパ大陸においてであったが、それは、そのようにして執筆された草稿の一部が「弟子」の1人であるジュネーヴ出身のデュモンに手渡され、彼によってフランス語に翻訳されて広まったためであった。そして、それらが後に英語に再翻訳されることになった。 このような逆輸入の形をとらない場合でも、ベンサムの著作は、それが書かれた時期、印刷された時期、出版された時期がしばしば異なっており、彼の思想形成を考えるうえで細心の注意を必要とする。例えば、彼の初期に属する代表的著作のひとつである『道徳および立法の諸原理序説』にしても、1770年代に書かれ、1780年に印刷されたが、新たに「序言」を付して出版されたのは1789年であった。他にもそのような例が少なからず見出されるが、本コレクションのリヴィングストンの蔵書中には、印刷されたばかりで表紙も付されないまま、ベンサム自身が署名して献呈したと思われる『憲法典』(第1巻)が含まれている。これなども、ベンサムの著作がいまだ出版される以前の試作本の段階で配布されたことがありうることを例証するものとして、きわめて貴重である。 本コレクションに所蔵される名誉毀損を罰する当時の法律を批判した『包装技術の諸要素』という著作は、次のことを示している。すなわち、それは1810年に印刷されたが、そのときには同法律による訴追の可能性を指摘する友人たちの警告にしたがって、著者・出版社・印刷社(者)を秘匿するために、表紙の下半分と奥付(最後の頁)とが切除された。そして、10年以上経過した後、訴追されないことが判明した1821年になって、新たに表紙や奥付を付して出版された。『議会改革計画』という著作の場合には、執筆されたのは1809−10年ごろであるが、さまざまな政治状況が必要とするようになった1817年にようやく出版された。しかも、その際、本文の7倍以上もの頁数にのぼる「序文」を付すという異常な構成と体裁を取ることになった。これら以外にも、複雑な経過をたどって出版されたことを示す著作が少なくない。本コレクションに所蔵される貴重な著作やパンフレットは、それらの点を書誌学的に解明することを可能にしている。 さらに、本コレクションに所蔵される『流通年金』という48頁の本文と2枚の表からなるパンフレットは、今日世界でその存在が確認される唯一のものである。ベンサムは1800年に同名の大部の草稿を執筆したが、その一部が1800-01年に少部数のみ印刷されたことが知られている。それは、かつて大英図書館に所蔵されていたが、第二次世界大戦時の空襲により焼失してしまい、それ以来どこでも発見されていない。この小さなパンフレットもまた、将来『ベンサム経済学著作集』の編集作業と刊行に際しては貴重な資料となるものである。 この他、中央大学図書館には、上記ユニヴァーシティ・カレッジおよび大英図書館に保管されているベンサム自筆草稿のほとんどすべてが、マイクロフィルムによって所蔵されている。そのうち、大英図書館所蔵の宗教関係草稿は、同図書館所蔵の原状に復元されている。 ブルーム書簡以上の著作やパンフレット、マイクロフィルム以外にも、本コレクションには、スコットランド出身のイギリスの政治家ヘンリ・ブルーム(1778−1868)のベンサム宛の自筆書簡が3通含まれている。ブルームは大法官・貴族院議長を務めたウィッグ派の有力政治家であるが、すでに1810年代初期から同じスコットランド出身のジェイムズ・ミルを通じてベンサムとも知己となっていた。ごく少数の友人に限られていたベンサム家での夕食会にもしばしば招かれ、これらの書簡が書かれた時期には両者の関係はきわめて親密になっていた。このころ交換された両者の書簡には、相互に「私の親愛なる息子」「私の可愛い小さな人形ちゃん」(1827年9月27日、11月30日、1828年3月10日のブルーム宛のベンサムの手紙)、「親愛なるおじいちゃん」(1827年10月6日のベンサム宛のブルームの手紙)と呼び合うほど親密であったことが示されている。この時期、ベンサムはすでに80歳になろうとしていたのに対して、ブルームは50歳を迎えようとする年齢の開きがあったからである。 しかし、同時により具体的な事柄になると両者の間には微妙な姿勢の違いがあった。ベンサムもその点に十分気づいていた。バウリング版『著作集』に収録されているベンサムのメモや書簡には、実際的な場面でのブルームの日和見的な態度を警戒する言葉がしばしば記されている。ブルームの方でも、ベンサムおよびベンサム派の人びとに対しては、友好的で親密な態度を示しつつも、具体的な点になると距離をおく姿勢を保ち続けた。その点は、とくに議会改革や大法官裁判所あるいは破産裁判所の改革問題では顕著であった。 本コレクションに含まれる3通の書簡は、1827年9月16日、22日および1828年3月10日の日付をもっているが、いずれもユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンに保管されているブルーム・ペーパー(ブルーム・コレクション)および大英図書館の関係文書には欠落していたものである。それらのうち、1827年9月22日付の書簡は裁判所の改革問題に関してブルームの見解を述べたものであり、他の2通では、当時ベンサム派の人びとも参加して設立しつつあったユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの英文学の教授ポストにバウリングを就任させることを強く要請するベンサムに対して、設立評議会の有力メンバーでもあったブルームの慎重な意見が婉曲に述べられている。彼は、バウリングの才能を評価しつつも、ベンサムの要請とは距離を置く客観的で冷静な態度に終始している。 これらの書簡のうち、1827年9月22日付書簡の後半の一部のみがバウリング版『著作集』第10巻574-5頁に収録されている。しかし、原文に照らし合わせてみると、明らかに誤読と思われる箇所が数箇所見出される。中央大学に所蔵されるこれらの書簡は、ベンサム・プロジェクトによって将来『ベンサム書簡集』にも収録される予定である。 これらの書簡を含め、本コレクションはベンサム研究および功利主義研究の第一次資料としては、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンおよび大英図書館を合わせたロンドン以外では世界でもっとも整備されたものであり、「英吉利法律学校」として創立された中央大学の伝統にふさわしいコレクションということができる。本コレクションについては「英文解題目録」が作成され、世界の主要な図書館・研究機関に配布された。中央大学の伝統および本コレクションに着目して、先のようにユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンから中央大学に対して『新ベンサム全集』の一環として『ベンサム経済学著作集』(4巻)を草稿から共同で編集し、オックスフォード大学出版局から刊行する提案がなされている。その後、さらにベンサム・プロジェクトから「ベンサム研究日本センター」を中央大学に設置する提案さえなされている。『ベンサム経済学著作集』の刊行は、ベンサム像と功利主義理解の革新をさらに推し進め、今日的課題の解決にとって功利主義が果たす重要な役割を改めて確認させる決定的な契機になるものとして、その実現が内外から注目されている。本コレクションは、そうした提案の実現に際しても大きな役割を果たしうるものである。 [記] ブルーム自筆書簡の解読には、本学経済学部教授デレク マサレラ氏のお世話になった。同氏のご協力に深く感謝申し上げます。 (中央大学経済学部教授 音無通宏) |
このページへのリンクの許諾は必要ありません
著作権について
| Copyright 2003 Chuo University. All rights reserved.